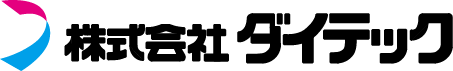はじめに
多くの人がもっと文章がうまくなりたいと考えています。うまく書けない人が、うまくなる方法はないのでしょうか。

私は30年以上にわたってライティング業務を行ってきました。
どうすれば文章がうまくなるのかについて、30年以上にわたる筆者のライター経験に照らして考えてみましょう。
前回までの振り返り
文章力向上をテーマにお伝えしてきたブログ、今回が第三弾(最終回)となります。第一弾では、文章力のカギは『素材の量』ということをお伝えしました。
第二弾では、その素材を増やしていくための具体的なトレーニング方法を、段階を追って見ていきました。まずは上手くなりたい文章の対象を絞り込み、それに沿ったお手本(教材)を見つけます。教材が決まったら、その内容をよく(深く)理解します。
ここまでが前回までのお話です。
今回は、文章がうまくなるためのアウトプット練習について紹介します。
アウトプットとは
しっかりとお手本の読み込み(インプット)ができたら、次はアウトプットに入ります。
語学学習では、読む・聴くをインプット、書く・話すをアウトプットと分けています。ここでも語学学習のメソッドに倣い、アウトプットの定義は、書く・話すこととしましょう。
文章のトレーニングですから、ここは「筆写」と「音読」となります。
たとえば、対象の文書になるべく近い形のフォーマットを用意し、そこへ教材と同じコンテンツを再現する、という方法を採っていきます。フォーマットに対して文字を埋めていく作業が『筆写』です。

また、教材の文章を頭から声に出して読んでいくことも、よいトレーニングとなります。これは『音読』です。
今回は、この筆写または音読の具体的な方法について述べてみたいと思います。
まずは、筆写からです。
筆写のやり方
さて、筆写したい対象が報告書や提案書であれば、ブランクのフォーマットが用意できると思います。
お手本とブランクフォーマットを並べ、大・中・小項目も忠実に、ひたすら文章を写していきます。
取扱説明書であれば、白紙スペースに図や画像などの位置をマークして、それ以外のテキストコンテンツの場所に、お手本通りに筆写していきます。

このように模擬レイアウトに書き込んでいく作業は、単純で短い語の筆記を繰り返すのとは違い、記憶のタグ付けが随所でできるため、いわゆる「体で憶える」のに効果的です。
手書きをすることが極端に減ってしまった現代生活ですから、筆写といってもPCでタイピングしたくなることと思いますが、ここは手で書くほうが断然トレーニングになります。文字を手で書く行為には、「体で憶える」という点で大きな意味があります。
どうしても手書きはやりにくいというなら、PCを使うのもよいでしょう。しかし、コピーペーストなどをしては本末転倒。文字キーの手打ち以外の方法は論外ですから、そのつもりで。
音読のやり方
音読の方法については、取り立てて難しい点はありません。教材文書の頭から、人に読み聞かせるように声に出して読んでいけばいいだけです。
注意点としては、表題や見出しなどもすべて読むこと、書いてある順番に読むこと、段落など意味の区切りがある箇所は発声を一旦止めて間をおくなどして、まとまりを意識して読むことです。
内容を口述で他人に説明(報告書であれば報告)しているつもりで音読すると、意味をしっかり考えながら読むことができます。
音読と筆写の比較
語学を習得するためには「音読」が効果的な練習の筆頭、というのは定説となっています。しかも、音読はやればやるほどそれなりに効果があるといいます。そのゴールは決して「丸暗記すること」ではなく、むしろ暗記してからの愚直な繰り返しこそが、言語を身体に染み渡らせる秘訣です。
文章力をつけるための筆写についても、同じことがいえます。しかし、筆写と音読が大きく違うのは、時間と手間です。音読と筆写について、ちょっと両者を比較してみましょう。

音読は当然ながら、手による筆写より断然速く行うことができます。たった1秒のあいだに日本語で数文字、英語で数ワードを発声可能です。
対して筆写は、単純で短い文章でも「一文字が何秒」の単位で時間がかかります。表現の巧みさを味わいながら、注意して書いたり何度か読み直したりしていると、さらに時間を費やします。
また、筆写に当たっては「コンテンツを再現」「できれば手書き」など、お作法について注文を付けましたが、音読は基本的に、お手本の文書を初めから終わりまで声に出して読んでいくだけであり、簡単です。
そして、音読はどこでもできます。電車の中など他人のいる場所でも、周囲に聞こえないくらいのボリュームで音読するのは、語学の定番の練習方法です。さらに暗記後はテキストを見る必要がなくなり、歩きながら、ジョギングしながら、料理・入浴・運転しながらと、日常の時間の中でいつでもできます。睡眠前に、照明を消した部屋の布団の中でもできます。
しかし筆写となるとそうはいきません。別のことをしながらできないのは言うまでもなく、暗い場所でも不可能です。
繰り返しで密度をかせぐ
このように、筆写練習には、音読に比べ手間と時間がかかるというデメリットがあります。現実的には、一回に筆写するのはA4サイズ1枚分程度が限度でしょう。あるいは、新聞の社説ぐらいの長さでしょうか。
こうして見ていくと、筆写練習については「やればやるほど」といっても限界があります。筆写によって、音読と同様に効果を上げるためには、密度を濃くする方法を採るしかありません。
その方法とは「同じものの繰り返し」です。

あれっ? 小学生が漢字を100回書いて憶えるのは、大人の学習には効率が悪いと前回言ったばかりでは? いえいえ、文字と文章とでは、少々条件が違ってきます。
文章は文字の連なりからできていて、文字よりも複雑な意味を構成していますから、文字よりは断然「記憶の引っ掛かりが多い」わけです。意味を持ち、引っ掛かりが多いものは、単純な繰り返しでも吸収しやすく、引き出しやすいのです。
そこで報告書なら報告書、取扱説明書ならそれ、同じ対象物を、何度も筆写することをお勧めします。もちろん、繰り返す回数が多いほど初めのうちは有効ですが、自分の持ち時間とも相談しましょう。
この点、短時間で数十回も繰り返せる音読のほうが効率的と思われるかもしれませんが、記憶の引っ掛かりの強さで言えば、作業の中でのビジュアル要素が多い筆写のほうに、軍配が上がります。
また、筆写といっても目と手による作業のみに留まらず、その中には音読ならぬ黙読の要素も含んでおり、音読と比べて筆写の優位性は低くありません。
結局どちらがいいのか
そういうわけで、音読と筆写には一長一短があります。
両方やるとより効果的に記憶できることも実証されていますが、実際にやるとなると、これは大変です。
大人の学習は、続けられる方法でなくてはならない(*)。つまり、簡単で短時間でできるやり方でなければいけません。

ここは「自分にはどちらがやりやすいか」「どちらが好みか」などで選べばいいと思います。
どちらの方法を行うにせよ、別のお手本へと移る小ゴールは「スラスラと音読(・筆写)できるようになる」です。完璧でなくても、8割程度でできれば、次の教材に移っていいと思います。
(* 子供の学習は、集中する訓練・続ける訓練の要素もあるため、大人のケースとは異なります。)
筆者の経験
筆者は、高校生時分に筆写を集中的にやった時期がありました。なにもそのころからライターを目指して訓練していたわけではなく、それが夏休みの宿題として出されたからでした。「夏休み42日間、新聞の社説を毎日ノートに筆写せよ」。学生に宿題の拒否権はありませんから、毎日これを続けました。

初めは文節単位でただただ見た通りに書き採るだけでしたが、夏休みが終わるころには、主張や意見を述べる論説文、つまり社説の論法の運び方やそのための語彙が以前より身に着いた感覚がありました。
音読については、小学校の授業で幾度となく行い、社会人になって学んだ文芸のコースでもやりましたが、音読を日本語文章のトレーニングとして行った経験はありません。しかし、英語のトレーニングのための音読を集中して行った時期はありました。音読のよいところは、アウトプットしながら自分の声で自然に再インプットされる点で、これにより音とリズムで内容が脳に定着しやすくなります。
最後に注意
さて、音読または筆写を実践する上での注意点をひとつ挙げて、この稿を終わりたいと思います。
それは「念仏や写経になってはいけない」ということです。(「念仏や写経」とは比喩であり、宗教的な意味合いはありません。)
音読や筆写する際に、とくにある程度文章を憶えてしまってからは、個々の文の意味が意識に上ることなく、言葉やテキストだけが上滑りの状態で進んでいることがあります。これを「念仏や写経」と表現しました。
写経・読経は、何も考えず無念無想で進めていくことが修行の姿といえます。
しかし、文章力を身に付けるための音読や筆写は、これではいけません。一度記憶してしまえば、お経のように無念無想の内にいくらでも唱えられ、書けますが、これは無意味です。文章の内容を憶え込んだら、むしろより丁寧に文意をかみしめながら、音読・筆写してください。
それが、あなたの中の(A)素材を増やします。
そしてそれこそが、自由闊達に(B)作業・(C)感知・(D)是正へとことばを運べるようになるための方法、文章がうまくなる方法です。
グッドラック!