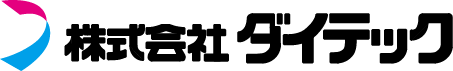はじめに
このブログタイトル (文章を上達したい) に足を留めた、画面の前のあなた。
もしかして文章がうまく書けないことで、報告や発信に苦戦した経験をお持ちか、いまなお苦戦していらっしゃるのではないでしょうか。
理由はともかく、多くの人がもっと文章がうまくなりたいと考えています。
しかも、「実際の文章がうまいかそうでないかにかかわらず」です。
むしろ文章が苦手な人よりも、そこそこに書ける人のほうが、もっともっとうまくなりたい!という欲求が強いかもしれません。

ではどうすれば、文章がうまくなるでしょうか。
その方法について言及したメディアはふんだんにあります。
書籍、雑誌の特集記事、Webサイト、動画、セミナー、塾、通信講座…この記事だって、当社のWebサイトを通してご覧になっているはずですね。
これらの媒体で紹介されている「文章がうまくなる方法」。あなたも、いろいろと探した中からいくつかは実践してみたかもしれません。
ではそれで、成果は上がっていますか?具体的には、うまくなったのが自分でわかる、他人からうまくなったと言われるようになった、などの結果が見られるでしょうか。
文章書きにはこれで終わりというゴールはありませんから、これでもう大丈夫!と文章技術の上達を保証することはできません。このブログを訪れていただけたのもなにかの縁です。
どうすれば文章がうまくなるのかについて、私の経験と照らして、一緒に考えてみましょう。
筆者は30年以上にわたってライティング業務をおこなってきました。
駄文(ダメな文章)を識別できるか
「文章がうまくなりたい」という人にも、経験値や習熟度の差があるものです。
これからそれをタイプ別にご紹介しますので、ご自分がどのタイプに当てはまるのか、考えながら読み進めていただければと思います。
まずは、駄文が駄文と識別できるかどうか、に分けられます。
だ‐ぶん【駄文】1. つまらない文章。へたくそな文章。 2. 自分の文章を謙遜していう語。
決して愉快な表現ではありませんが、プロのライターから見てまだまだ直す余地のある文章を一括りで、ここでは「駄文」と呼ばせていただきます。
「書いたものが自分でもいい文章とは思えないが、どこをどう直せばよくなるのかわからない」。辛いことでしょうね。でもこれは、駄文が識別できている状態です。
この状態の人を、ここでは『自覚がある人』と呼ぶことにします。
一方、駄文を駄文と認識できない人、上の例に倣えば『自覚がない人』というのも少なからずいらっしゃって、さらに次の2パターンに分けることができます。「書いたものが自分では悪くないと思えるのに、上司から絶望的に指摘が入り、指摘を見るとそのとおりだと思う」。これも辛いでしょうね。

それから、
「自分では悪くないと思える文章に、上司からは絶望的に指摘が入るが、もらった指摘を見てもなぜそう直されたのか、まったくわからない」。これはこれで、辛いでしょうね。
前者を『認識できる人』、後者を『認識できない人』と呼ぶことにします。
では、『自覚がある人』はなぜ自力でいい文章が書けないのか。
『認識できる人』はなぜ初めに駄文と認識できないのか。
『認識できない人』は指摘を受けてもなぜ駄文と気づけないのか。
そこを考えてみましょう。
それには、上記の3タイプに加え、そこそこに文章が書ける人=『書ける人』というのも登場させておきたいと思います。ここでいう『書ける人』とは、プロのライターはもちろんですが、あなたの文章にダメ出しをする立場の人全般を指すことにしましょう。
あなたが苦労してまとめた報告書を「これじゃわからん」(広島弁)と突き返す上司も、これに則って『書ける人』です。
『上手な文章を書ける人』はなぜ書けるのか
さて、『書ける人』の頭の中には、よい形とされる定型文や文章のまとまった流れが数多くストックされています。((A)素材)
誤解をおそれずにいうなら、『書ける人』はその膨大な定型から表現を引き出して並べ、文章にしているにすぎません。((B)作業)
書いた文中に
・間違った文
・間違ってはいないがそぐわない言葉選び
・いまひとつ違和感の残る表現
などがあっても、すべてこの素材データから照らして感知でき((C)感知)、ニュアンスを改善できる((D)是正)のが、『書ける人』です。
これを背景に、文章を細かい部分で直したり、全体構成で直すことで、結果的にうまい文章に仕上げているといえます。
『書ける人』が実行している、上記の(A)素材→(B)作業→(C)感知→(D)是正の流れと比較しながら、『自覚がある人』『認識できる人』『認識できない人』の状態を見てみましょう。
文章がうまくかけないのはなぜ:『自覚がある人』
まず、『自覚がある人』は、自分がおこなった(B)作業のでき具合に不満を抱いていることから、(C)感知はある程度できていることになります。
しかし、うまく(D)是正するやり方が見つかりません。
これは、(A)素材の量が十分でないためです。書いた文章との比較はできるものの、引っ掛かった箇所についてさらによい表現を見つけ出せるほどの(A)素材の量がない、というわけです。
文章モデルのストック=(A)素材が多くあればあるほど、(D)是正のための語彙や表現の選択肢も多く持っていることになります。これにより文章推敲の自在度が高まり、いい文章へとつながります。
文章がうまくかけないのはなぜ:『認識できる人』
次に、『認識できる人』は、初めは自分の(B)作業のできはよいと考えていたものの、上司の指摘から駄文と気づかされます。
つまり、指摘を受け入れた時点で、初めて(C)感知の一部ができたといえます。
なぜ初めからそれに気づかなかったのかといえば、(C)感知のための材料、すなわち自分の文章と比較する(A)素材の量が、足りなかったからです。
(A)素材が多くあればあるほど(C)感知がよくはたらき、前項と同様の理由で(D)是正の質も向上します。
そしていい文章へとつながります。ここでも、ポイントは(A)素材なのです。
文章がうまくかけないのはなぜ:『認識できない人』
さらに、『認識できない人』は、自分の(B)作業のできはいいと考えており、さらに上司の指摘を受けても、なぜ指摘されるのかその理由がわかりません。
これは、(A)素材の絶対量が少なすぎるためです。言い換えるなら、それまで触れてきた日本語文章の量が、文の良し悪しを比較判断できないほど絶対的に少ないのです。(この定義に当てはまらない例は存在します。これについては、方法論の章で述べます。)
このタイプの人は、これから『認識できる人』へ、さらに『自覚がある人』『書ける人』と上達していくために、まず(A)素材の絶対量を桁違いに増やす必要があります。
つまり、このタイプの人も上記の人達と同じように(A)素材が重要なのです。
人間の思考を手本に作られたAIを、人間の手本に?
なぜ、これらのことが言えるのでしょうか。
それは、いまや人類の最先端技術の一角を担う『AI』の世界、とくに『文章生成AI』の仕組みを考えていただければわかりやすいかと思われます。
文章生成AIは、人間のような対話ができるだけにとどまらず、その内容も適格で合理的です。

その背景には、多くの量の情報を読み込み、そこからもっともふさわしい回答文を構成するという、人間がやるのと同じような仕組みの存在があります。
人間と違うのは、文章生成AIは(A)素材の量が桁違いに多いという点です。
であれば、(A)素材の量が足りていないとされた前述の『自覚がある人』『認識できる人』『認識できない人』への処方箋も、だいたい浮かんできます。
文章生成AIには到底かなわないまでも、現状よりも(A)素材の量を増やすことが、それも爆発的に増加させることが『書ける人』へ近づくことにつながります。
まとめ
文章がうまくなるためには(A)素材の量を大幅に増やす、つまりはよくできた日本語文章を大量に取り込んで、自分の中にうまい文章の材料を多く持つこと、というのが、今回のまとめとなります。
では具体的にどうやれば、もっとも効率よく(A)素材を増やすことができるのでしょうか。
次回はこの方法に迫ってみたいと思います。