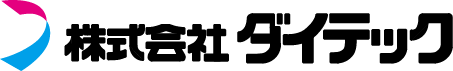はじめに
多くの人がもっと文章がうまくなりたいと考えています。うまく書けない人が、うまくなる方法はないのでしょうか。
私は30年以上にわたってライティング業務を行ってきました。
どうすれば文章がうまくなるのかについて、私の経験と照らして一緒に考えてみましょう。
注:このAI全盛のタイミングで、今さら「文章力」⁉・・と
疑問にお思いのあなたへ
今やビジネス文書、論文、手紙文、翻訳文など、自分が書きたい文章は、生成AIを使って自由に生み出せる時代です。ストーリーやオチのある創作文さえ作ってもらえます。

しかし、生成AIも万能ではありません。
「イマイチ伝わらない・・」
「言いたいことが、少し違うような・・」と感じたことはないでしょうか。
それを解決するためには、やはり個人の文章力が必要になります。AIが書いた文章のどこがおかしいのか、どこを直せばもっと良い文章になるのか、それを判断しなければいけないからです。
文章力を上げることは、AI技術を使いこなせる能力にもきっとつながっていきます。
前回の振り返り
まずは前回の内容を振り返りましょう。前回の記事では、書ける人がなぜ書けるのか、そこに近づくポイントは何かについてお話しました。
『書ける人』の技術とは、以下のような構成になっています。
・頭の中に、よい形とされる定型文や文章の素材が数多く蓄積されている((A)素材)
・そこから表現を引き出して並べ、文章化している((B)作業)
・書いた文章を(A)素材データと照らして、よくない部分を感知できる((C)感知)
・よくない部分のニュアンスを改善できる((D)是正)
(B)作業・(C)感知・(D)是正がうまくできるかどうかは、すべて(A)素材の量によるところが大きいと考えられるため、文章がうまくなるためには、どうも(A)素材を爆発的に増やす必要がありそうだ、ということが推測できました。
ここまでが前回のお話です。今回は、この(A)素材を増やす方法について考えてみましょう。
頭の中に素材を増やしていくには
『書ける人』は、どうやって文章技術の背景となる(A)素材を蓄積してきたのでしょうか。
言ってしまえば、幼少よりそれはそれは多くの文章を読んできたからでしょう。
これに尽きるといえます。いわゆる『読書家』と称される人々などは、その典型です。
では、そういう人たちと並ぶために、読書量で追いつくことはできるのでしょうか。
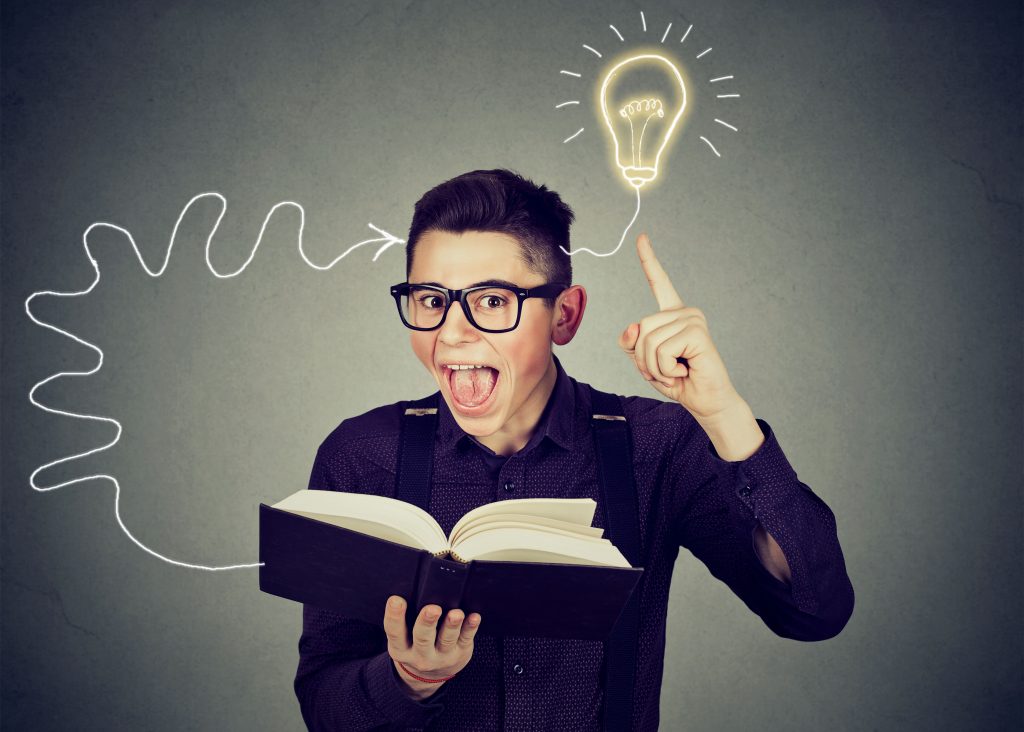
身も蓋もない言い方となってしまいますが、これまで文章を大量に読んでこなかった人にとって、大量に読んできた人に読書量で追いつけるよう、いまから努力を始めることは、現実的ではありません。
なぜなら働き始める前から、彼ら彼女らにはすでに膨大な量の読書の蓄積があるためです。
仕事を引退して、一日中本を読んで過ごす生活ができるなら、いつか読書量で追いつくことが可能かもしれませんが、当ブログの読者の大半はこの環境に当てはまらないでしょう。
一般的な読書の量で追いつけないとなると、『書ける人』に近づこうとしているあなたが、文章技術の背景となる(A)素材を蓄積するには、どうしたらいいのでしょうか。
効率的なトレーニングはあるのでしょうか。
まずは対象を絞り込もう

読書の量で追いつけないのであれば、大人の語学学習と同じように、ある程度シチュエーションを絞った素材を教材とするのがよいでしょう。
語学学習の教本では『あいさつ』『自己紹介』『趣味をたずねる』など、絞り込んだシチュエーションで小単位の学習ステップを進めていくのが通例です。
また、大学入試や資格試験などの試験対策も、これに似ています。
試験において、出題範囲とされる領域すべてを網羅できていれば理想的ですが、多くの人は『過去問』などで出題傾向を把握してそれを中心に学習したり、過去に出題されていない分野は捨てたりして、学習の効率化を図るのではないでしょうか。
(A)素材を増やすための読書も、やみくもに文章を当たるのではなく、目的に沿って絞り込むことをお奨めします。
お手本を厳選しよう
文章がうまくなりたいあなたは、具体的には何を書きたいのでしょうか。
自分がうまく書きたい文章の対象を決め、まずはその「よいお手本」を用意しましょう。
報告書をうまく書きたい人は、上司や同僚が書いた過去の「よいとされる」報告書。
提案書をうまく書きたい人は同様に、よい提案書。メール文章も然りです。

当社のような「取扱説明書」制作の仕事で文章技術の向上を目指したいのであれば、当然ながら用意するのは「よくできた取扱説明書」ということになります。
これらを中心に、インプット以外の方法も混ぜながら集中して取り込んでいくのが効果的と思われます。
ただし、注意があります。
それは、ネット記事そのものを、決して教材としないことです。
素材となるよいお手本のファイルをWeb上から探してくるのはいいのですが、Webに上がっている記事そのものには、目を覆いたくなるような悪文が蔓延しています。昨今は、有名な通信会社が発信するニュース記事でさえ、これに当たります。
悪文をわざわざ学ぶ必要はありません。それでなくても日ごろからそのような悪文を読まされることで、悪文のスタイルはあなたの脳内に刷り込まれています。一日の悪文摂取許容量を超えないことにも注意しましょう。
お手本をよく読んで理解しよう
よいとされるお手本が用意できたら、よく読んで理解しましょう。まずは一通りよく読み、全体の意味、論理構成を理解します。
読めていない(深く理解していない)のに分量を多く読んでも、(A)素材は増えません。
ことばを憶える子どものように、またはAIのように、極大量のパターンに短期間で接触できるなら別ですが、そうでない大人には個々を深く理解して確実に身につける方法が効率的だと思われます。
深く理解することの重要性は、読書量が割と多い人にも当てはまることがあります。
自ら読書好きと自覚し、実際に読書量の多い人でも、まれに文章が書けない人がいます。私の経験では、ここ20年ぐらいのあいだでも数人いました。
このタイプの人に、たくさん読んで(A)素材を増やせと説いても、ナンセンスです。本人は多く読んできているつもりだし、実際にそうなのですから。
多読家でありながら文章が書けない人が存在する事実は、私にとっていまだに大きな課題です。

まだ仮説の域を出ませんが、もしかすると彼ら彼女らは、ことばを表面的に眺めるだけで、前述した「深い理解」をしないまま読み進めているのかもしれません。悪くいえば、常に上滑りの状態で読んでいる。
そのため、文章理解(ストーリー理解)ができている自覚は本人にあるものの、文章細部への観察となるとほとんどできていない。その結果、読書が(A)素材を増やすことにつながっていないのではないでしょうか。
これは、ビジネス書などの実用書を速読する人にもいえそうです。
ビジネス書を読む多くの方が、キーワードだけを拾いながら、文章の細部ではなく要点だけを求めて読む「Skimming」という読み方をしていることと思います。
なぜなら、ビジネス書では抽象的・概念的な思考が多く語られる特徴があり、読んでいても小説のように情景が浮かぶことはなく、またその必要もないために、深く読まずとも読書の目的が達せられるからです。
お手本理解の次にすること
文を深く読むことの重要性は理解していただいたとして、話を元に戻しましょう。
教材を決めて、しっかりと読み込み(インプット)ができたら、次はアウトプットに入ります。
アウトプットも読み込みと同じく、これ自体はただの練習過程にすぎません。この段階ではまだ、自分の力でいい文章が書けるわけではありません。
目的は、手本とする文章を自分の中に取り込んで、自分の作文として自在に書き出せることです。
早い話、文章を記憶するためにアウトプットするわけですが、小学生のように同じ文字を100回書いて憶えるのは効率が悪すぎます。ここは大人の知恵を駆使したいところです。
次回は、具体的なアウトプットの方法についてお伝えします。