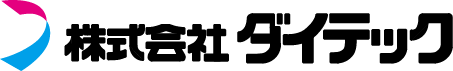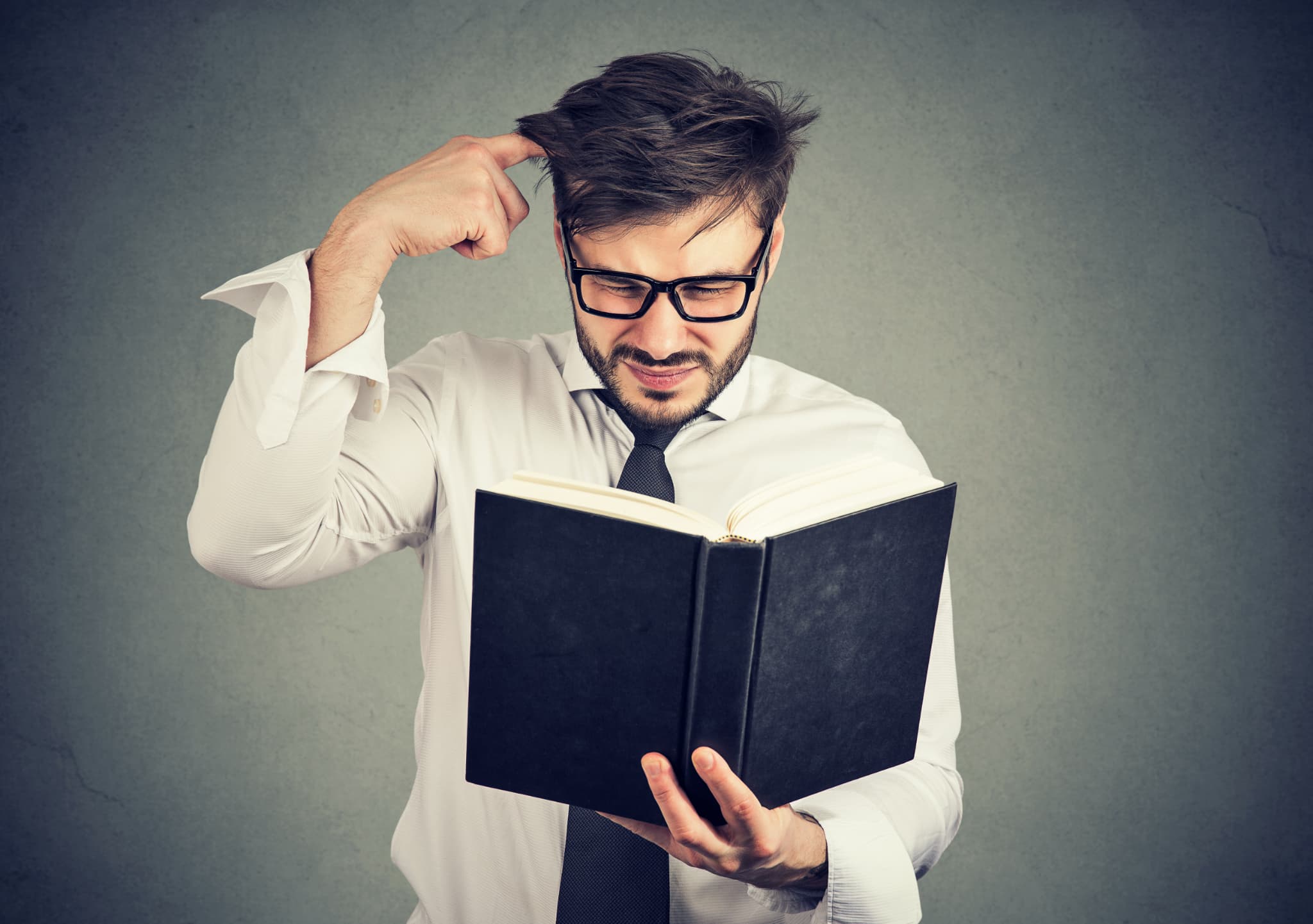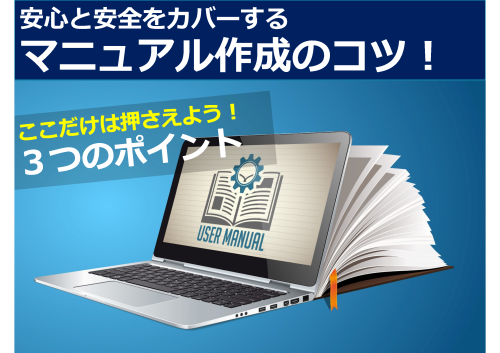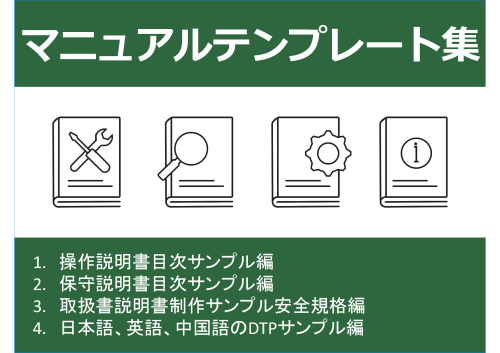はじめに
みなさんは、取扱説明書に記載されている安全に関する警告文や注意文を読んでいますか?
そもそも取扱説明書を読んでいないなんてことありますか?
正直、これを書いている筆者も、取扱説明書は困ったときに読む程度です。
本来、安全に関する項目こそ、ユーザーは真っ先に読まなければいけないのですが、ほとんどが分かりきった内容なので、ついつい読み飛ばしてしまいます。
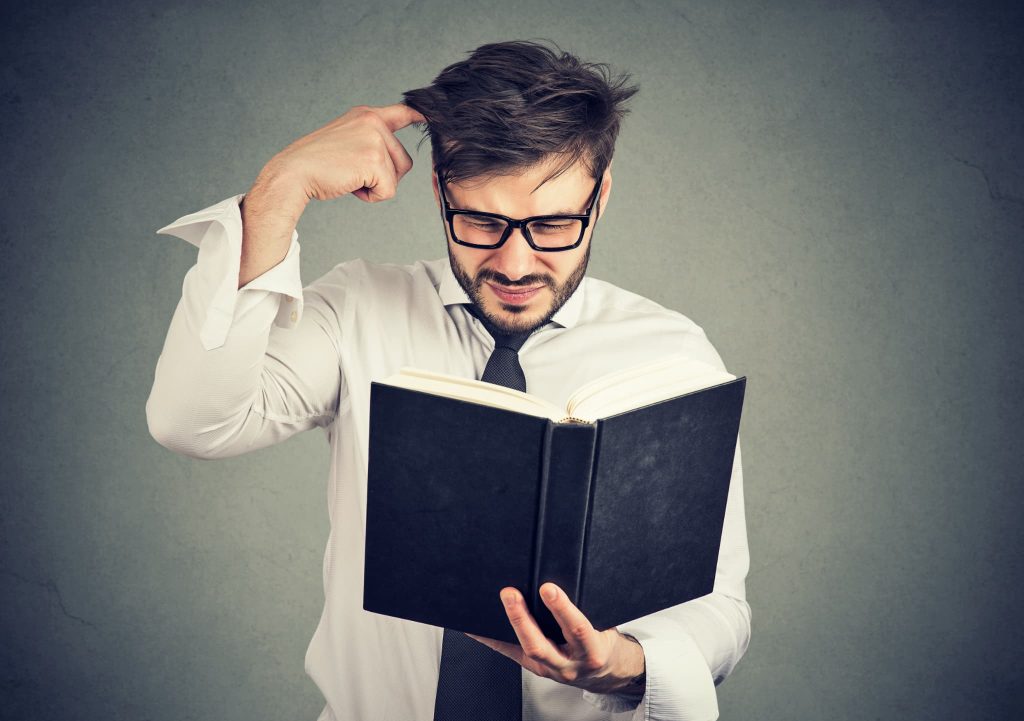
製品や機械をユーザーが安全に使用するために、危険を回避する方法は必ず取扱説明書に記載しなければなりません。しかし、記載する情報が多い場合、何をどこに記載してよいか迷うことがありませんか?
本記事では、安全上の注意を記載する箇所や内容について、警告や注意事項が多い産業機械の取扱説明書を例に紹介していきます。
安全上の注意はまず情報の整理から
家電製品とは違い、産業機械や輸送車両のような規模の大きな機械・装置では、その取扱いに多くのリスクを伴います。電気、空圧、水圧などで作動するモノや高速で回転するモノ、高温になる箇所など、機械や装置にはどうしても危険が生じるモノや箇所があるのです。
そのため様々な危険情報を整理し、必要な箇所に適切な警告文や注意文を記載することが、取扱説明書に求められます。
通常、警告・注意すべき内容は製品のリスクアセスメントに基づき検討されます。そのため、どこで・どのような状況で・どのくらいの頻度で発生するのか、整理されたリスクアセスメント情報があります。
まずは、そのリスクアセスメント情報を警告文に読み替えることで、
- どのようなときに
- どのような頻度で
- どのような危険があり
- どのような回避策があるのか
を組み立てることができます。
ここでは、その中の「どのような時に」を基軸に、警告文・注意文の記載方法を紹介していきます。

「どのような時に」を基軸にすると、記載は3つのパターンに分けられます。
(1)全体的安全メッセージ(安全章に記載)
対象製品全体を通して、人身または物損事故を防ぐためのガイドラインとなる情報を記載します。
(2)章の安全メッセージ(章または節、項の冒頭に記載)
ある章(または節、項)のみに関係する安全上の注意を記載します。
(3)組込み安全メッセージ(手順内に個別に記載)
使用手順の説明に関係する安全上の注意を記載します。
ただし、使用者の生命に影響を及ぼすリスク情報については、「探さなくても読める」箇所に必ず記載してください。
それでは詳しく見ていきましょう。
全体的安全メッセージ
全体的安全メッセージは、対象製品全体を通して、人身または物損事故を防ぐためのガイドラインとなる情報を記載します。
通常、安全の章または分冊された安全説明書に記載します。
ここに記載する安全上の注意には、一般的に順守が必要な「一般順守事項」と製品や機種特有の「特別順守事項」の二つがあります。
一般順守事項
一般的に作業者や管理者等全員が守るべき安全上の注意を記載します。
作業者の身だしなみ、作業場の整理整頓、製品の改造禁止などがこれにあたります。
これは対象製品の機種が異なってもほぼ同じ内容になります。
特別順守事項
対象製品・機種特有の安全上の注意を記載します。
製品に搭載されている部品や特定の仕様にかかわる安全上の注意がこれにあたります。
対象製品の機種が異なると、記載内容が変わる場合があります。
製品特有でかつ複数の章に共通する安全メッセージであれば特別順守事項に記載することになります。
上記2つの事項は、さらに禁止事項と強制事項に分けるか、または危険度で分けて、安全上の注意を箇条書きで記載します。
記載項目が多い場合は、製品の材質や作業条件など、カテゴリー別にわけるとさらによいでしょう。
章の安全メッセージ
次に、章の安全メッセージについて紹介します。
一般的に取扱説明書は、機械の運転操作、保守点検、据付・組立など、作業別に「章」を分けて構成されます。
運転操作の章であれば、運転前や運転中の注意事項などが安全上の注意にあたります。
例えば「可動部に近づかない」、「基準を超えた状態で運転しない」などが挙げられます。
保守点検の章では、保守点検時にしかアクセスしない箇所に関する注意事項がこれにあたるでしょう。
例えば「制御盤にアクセスする前に電源を切る」、「管理者以外、勝手に使用してはいけない」などがこれにあたります。
据付・組立の章では、製品の運搬や吊り上げ作業に関する注意事項などがこれにあたります。
例えば「運搬中に他の作業者を近づけない」、「吊り荷の下に入らない」などがあります。

このように、各章の内容に沿った安全メッセージを選び、各章冒頭に記載します。
各メッセージは、全体的安全メッセージと同様、禁止事項と強制事項に分けるか、または危険度で分けて、箇条書きで記載します。
なお、章の安全メッセージとして記載した内容を、全体的安全メッセージとして記載するかどうかは、危険度や発生頻度により判断します。
補足ですが、各章の安全メッセージを全体的安全メッセージとして重複記載するなど、複数の箇所に同じ警告文や注意文を記載する場合は、用語や書き方の不統一、誤記を生む原因となるので注意が必要です。
組込み安全メッセージ
組込み安全メッセージは、手順内に記載する安全上の注意です。
作業をしている最中に起こりうるリスクを説明するには、安全の章や各章の冒頭に記載するより、手順内に記載したほうがより的確に安全メッセージが伝わります。
そこで注意すべきことは、「警告文や注意文は、前後の本文と区別すること」です。警告記号やシグナルワードを使用して、警告文や注意文を目立たせる必要があります。また太字を使用したり、枠や仕切りを設けたりして本文と区別することも必要です。
ただし、作業手順内に警告文や注意文を挟み込むと、一連の手順が分断されて読みづらくなる恐れがあります。
そのため、安全上の注意としてではなく、そのまま作業手順として記載する方法もあります。

例えば、その安全上の注意が「必ずしなければならない」場合、この方法が可能です。手順として記載すれば、一連の作業として必ず実施するので、安全が確保できます。
「ロックアウトをします。」や「機械の電源を切ります。」などがこれに該当します。
ただし、「してはいけないこと」の場合は、警告文や注意文として記載する必要があります。
補足ですが、特定の作業手順に当てはまる安全上の注意の場合、組込み安全メッセージとして記載する方法は有効ですが、どんな作業手順にも当てはまる場合、全体的安全メッセージ、または章の安全メッセージに記載することをお勧めします。用語や書き方の不統一、誤記を防ぐことができます。
まとめ
今回は安全上の注意の記載方法について、産業機械の取扱説明書を例に紹介してきました。
安全に関する記載は多くなりがちですが、本記事で紹介したように情報を整理し、どの内容を、どの箇所に、どのように記載するかを決めれば、よりわかりやすくなるのではないでしょうか。
そのときに重要になるのは、「どのような時に」あるいは「どのような状況で」です。これを目安に情報を整理すれば、自ずと迷わなくなることがお分かりいただけたかと思います。
ダイテックでは製造業のマニュアル作成改善を検討する際に、考慮すべきポイントをまとめた入門資料「安心と安全をカバーするマニュアルづくり 3つのポイント」「なぜ読むマニュアルから『見る3Dマニュアル』が増えているのか?わかるガイド」をご用意しました。本資料は、マニュアル作成改善をしたい方には必見の資料です。ぜひダウンロードいただき、ご覧ください。