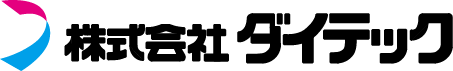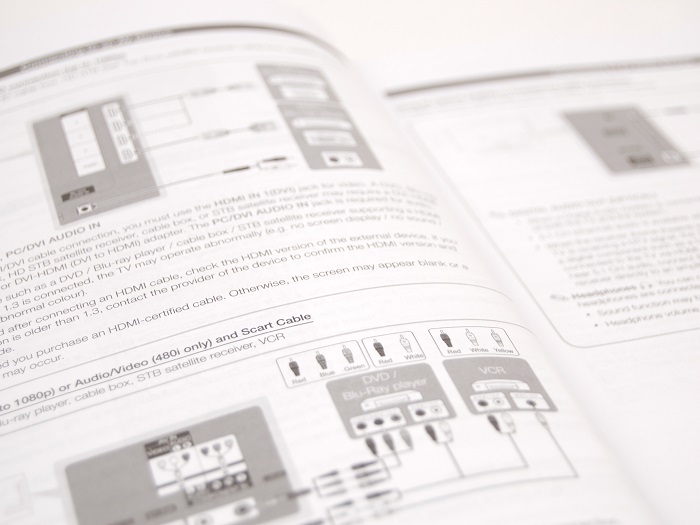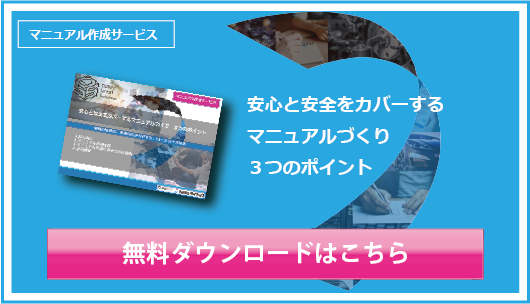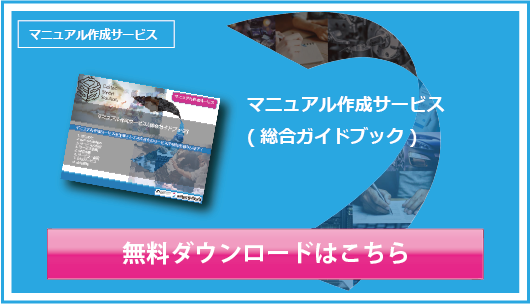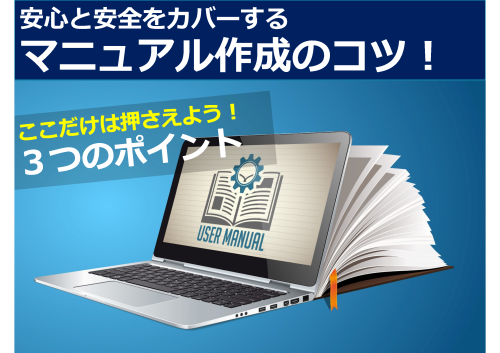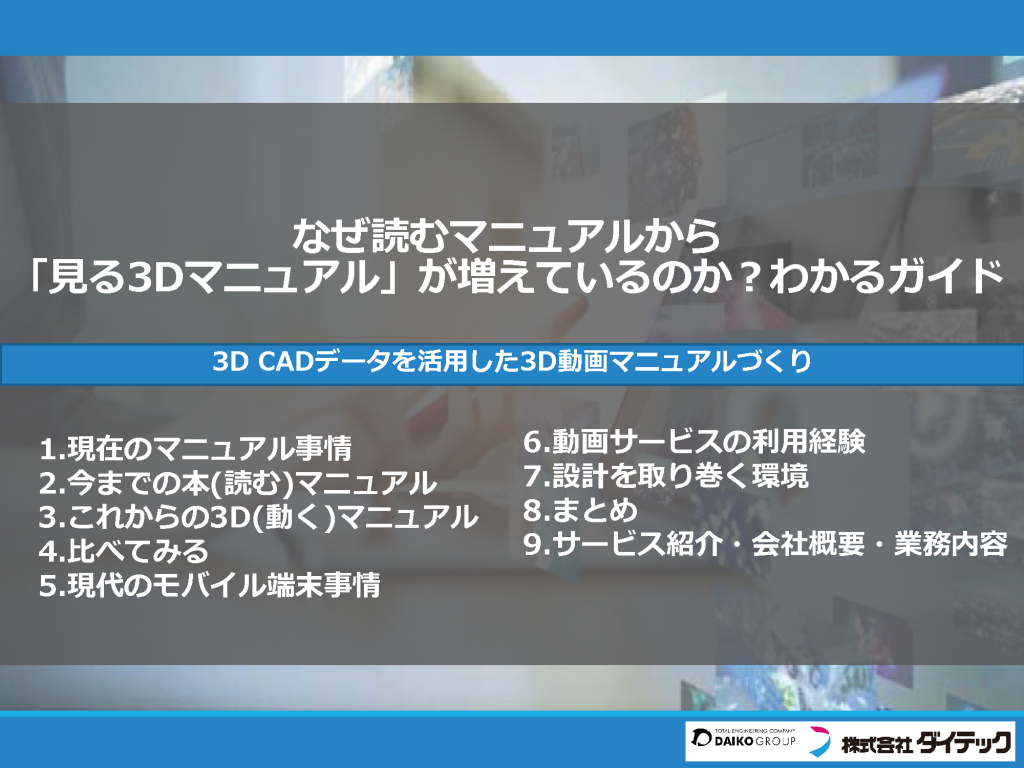序章
ご訪問ありがとうございます。このページをご覧になっているということは、今まさに「マニュアル作成ができる会社を探している」という状況かと思います。
そのきっかけは何でしょうか?
- 「自分で作成できるけど、本業の設計が忙しすぎて手が回らない」
- 「手順や機構の解説は得意だけど、PL対応や国際規格までどうやって調べればいいかわからない」
- 「会社のルールに則ってマニュアルを作成しているけど、ルールが古くて不安」
- 「新しく海外への輸出が決まったけど、これまでのマニュアルで問題ないか」
- 「顧客からWeb配信の要望があるけど、どう対応すればいいかわからない」
- 「上司はデータの有効活用を求めるけど、何をどうすればいいかわからない」
マニュアル作りは、一見簡単そうに見えて、実際には複雑な要素が絡みます。その上、あなたの課題に合った依頼先を探すとなると、さらに悩みは増えます。
しかし安心してください。マニュアル作成会社を選ぶときに押さえておくべき3つのコツを理解すれば、候補の絞り込みがぐっと簡単になります。本記事では、最適なマニュアル作成会社を選ぶためのポイントを、わかりやすく解説します。
マニュアル作成の会社や企業の違いや特色は?
マニュアル作成会社の違い
まず知っておきたいのは、「マニュアル作成会社は誰でも依頼を受けられるわけではない」ということです。
- メーカー系子会社:親会社系列の業務のみ対応
- 外部対応可能なメーカー系列会社:外部企業の依頼も引き受け可能
- 独立系制作会社:幅広い企業に対応
公式サイトで「見積依頼フォーム」や「パートナー募集ページ」がある会社は、外部依頼が可能な目安になります。
小さなポイントですが、「問い合わせフォームが求人だけ」という会社は、外部からの依頼は原則不可です。いくら実績があっても、依頼できなければ候補には入りません。
マニュアル作成会社の特色
候補企業が見つかったら、次は特色や得意分野を確認しましょう。
- 自社課題に合った解決法を持っている会社か
- 特定の製品分野に強みがあるか
- 規格や法規対応が可能か
これらはWebサイトや過去実績を確認することで、おおよそ判断できます。
マニュアル作成会社別の得意分野を知ろう
マニュアル作成会社をいくつか見つけたら、次は「課題を解決してくれそうか」を見極めます。
マニュアルは「製品分野」と「資料の種類」によって作り方が大きく異なります。例えば:
- 産業機械やプラント設備向けマニュアルは、専門知識と法規対応が重要
- 家電やスマートフォン向けマニュアルは、ユーザー向けのわかりやすさが重要
- Web配信用マニュアルは、デジタル対応や動画活用の経験がある会社が望ましい
ポイントは、「あなたの会社で扱う製品に近い実績があるか」です。畑違いの分野に依頼すると、時間や費用が無駄になることもあります。
公式サイトの「主要取引先」や「パートナー企業」をチェックすることで、その会社の強みや得意分野を把握できます。IoT対応や海外企業との取引実績も、この情報から推測可能です。
あなたに最適なマニュアル作成会社を選ぶ3つのコツ
ここからが本題です。マニュアル作成会社を選ぶときに押さえておくべきコツは、次の3つです。
- コスト感
- 専門分野
- 対応可能な規格や法規
1. コスト感
会社規模により、提示価格や対応力が異なります。
- 小規模(社員20名まで):SOHOやベンチャー企業、コストは低め
- 中規模(30〜100名):中堅クラス、規格や法規の専門スタッフが在籍
- 大規模(150〜200名以上):大手、安定感は抜群だが価格は高め
「予算は厳しいけど、安心感も欲しい」といった場合は、コストと納期、対応力のバランスを見極めましょう。
2. 専門分野
会社の得意分野はWebサイトの「主要取引先」や「パートナー企業」を確認します。
- 建設機械、食品製造装置、プラント、オーディオ、スマートフォン、船舶設備など
- 実績がある分野に依頼することで、完成度が高く、トラブルも少ない
3. 対応可能な規格や法規
輸出や法規制への対応能力も重要です。
- 北米、EU、中国向けの規格対応実績があるか
- 見積依頼時に仕向け先を伝えることで、適切なマニュアルが作成可能
規格対応が不十分だと、せっかくのマニュアルも役に立たなくなることがあります。
まとめ
マニュアル作成会社を選ぶ際は、以下の3つのコツを押さえると失敗が少なくなります。
- コスト感:会社規模と予算のバランス
- 専門分野:自社製品に近い分野の実績
- 対応可能な規格や法規:輸出や規制に対応できるか
これらを意識することで、「苦労せずに最適な制作会社に出会える」可能性が高まります。
マニュアル作りで悩んだ際は、ぜひ専門のマニュアル作成会社に相談してみてください。きっと解決策が見つかります。