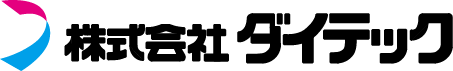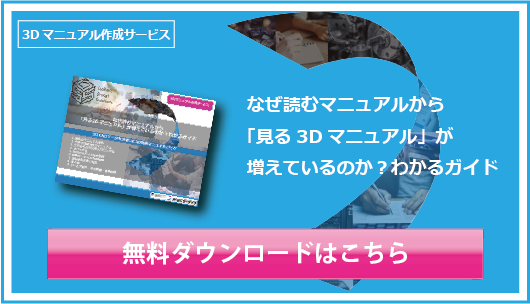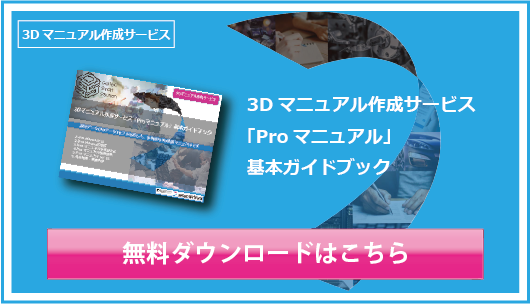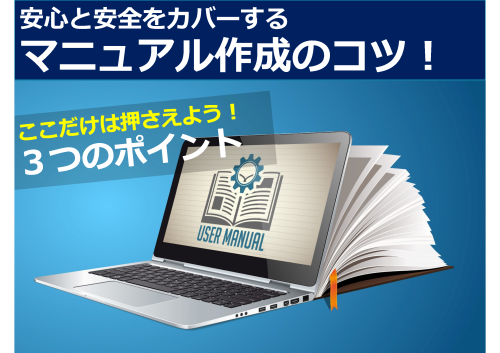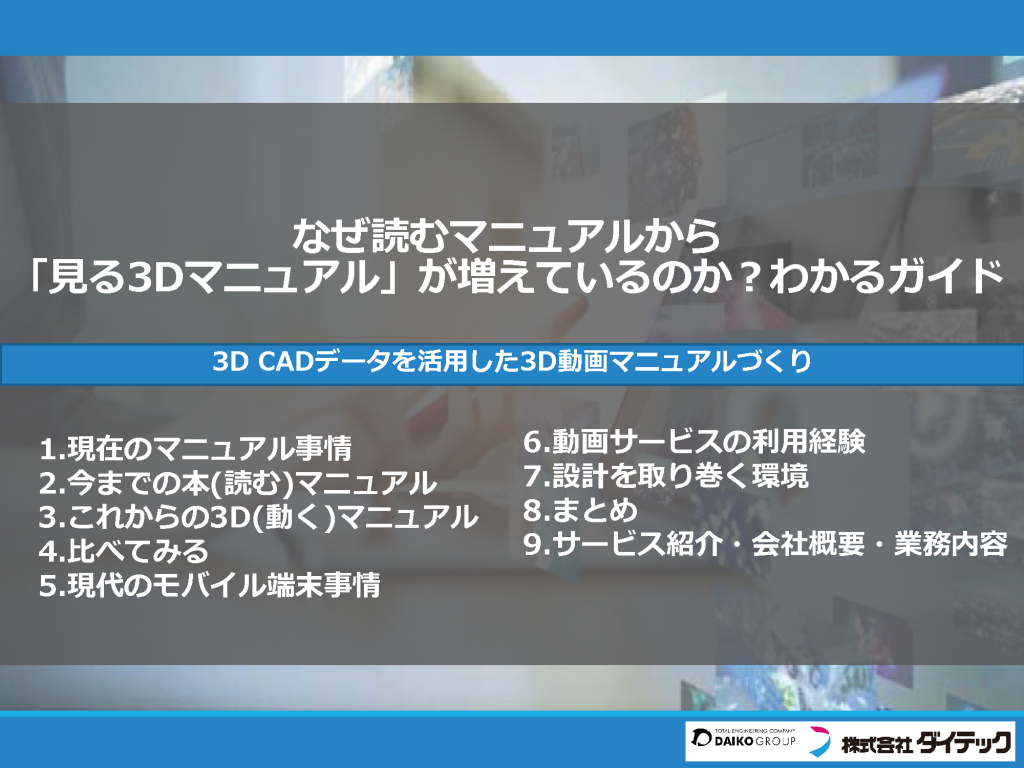序章
当社は、3DとAR技術を利用したマニュアル作成(取扱説明書)の将来性に期待しています。以前は展示会に出展し、多くの方へ身近なARトリセツ(炊飯器にiPadをかざすと該当ボタンの取扱説明書の操作手順が表示される事例)で、実際にご覧頂きました。また、複数のスマートデバイスを試しながら、マニュアル作成の効率化を図り、AR技術を取り入れたマニュアルも紹介していました。
当時のお客様へ伺うと、「興味はあるけれど、価格や制作の技術、工数確保を得ることが難しい」といったご意見を頂戴しています。良い技術であっても、取り巻く環境が伴わなければ、その効果を利用できません。
現在は環境が大きく変化し、通信速度の向上(5Gなど)やデバイスの進化、3Dデータの軽量化が進んだことで、ARマニュアルは再び注目を浴びています。本記事では、3DデータとARを活用したマニュアル作成のメリットと課題、そして将来性について解説します。
マニュアル作成における3Dデータ活用の実例
従来、マニュアルに掲載するイラストは、写真や図面をもとにイラストレーターが一から描いていました。現在では、設計・製造工程で作成した3Dデータを流用し、編集ソフトで角度を変えたり加工したりして、マニュアルに利用するケースが増えています。
- パーツ展開図:3Dビュワーを用いれば簡単に作成可能
- デジタルマニュアル:Webやアプリで表示し、拡大縮小や回転操作を伴う解説が可能
- アニメーション表現:動き・強調・色味を加えることで理解が格段に向上
重要なのは「マニュアル作成専用に3Dデータを新規作成する必要はない」という点です。設計や製造で既に利用しているデータを二次活用すれば、効率的かつ低コストで高品質なマニュアルを提供できます。
つまり、3Dデータの活用は製品価値を高めるだけでなく、マニュアル制作工程の効率化にも直結するのです。
マニュアル作成で3Dデータの有効活用を強く訴えるワケ
これまで組図レスの話の際に、「2次元の図面がないと、現場で3D CADは扱える人材が少ないから大変となる」といったスキル面の不安や、「現場の油まみれの手、作業中の難しい体制、工場に設備を導入する費用が足りない」など環境面での懸念から、導入が難しいという声を聞きました。
数年前であれば、それも仕方がない判断であったのかもしれません。しかし、3Dデータを取り巻く環境は著しく変化し、現場環境の快適性も求められ、いろいろな改善がされているようです。データ容量も軽量化され、アプリだけでなく、アプリ無しでWebブラウザ表示も可能な時代が訪れています。
若い人材を求めるにも、3D CADを積極的に導入し、これまでとは異なるアプローチで人材を確保したいといった企業様にとっても好機です。これまで縛られていた2次元化から解放することで、全く違う“考え方”の製品やマニュアルがお客様のもとに提供できるようになるのではないでしょうか。
「読むマニュアルから、見るマニュアルへ」
3Dデータが扱えるようになれば、後工程となるマニュアル作成工程においても効率化が期待され、閲覧時には表現の幅が増すマニュアルの可能性が見えてきます。
後ほど紹介するARとも相性がよいのが3Dデータです。誰もが容易にコンテンツ作成できるようになれば、今後益々現場で見かける機会が増えてくるのではないでしょうか。
マニュアル作成の会社が考えたこれまでのAR技術活用の限界
当社が数年前に展示会で出展した「3D×ARマニュアル」では、HMD(ヘッドマウントディスプレイ)を使い、実機に3Dデータを重ねて点検手順を説明するデモを行いました。
紙やHTMLマニュアルでは不可能な情報量を提供できましたが、当時はデバイスの扱いにくさや転送速度の問題があり、実用化にはあと一歩届かない状態でした。
それでもこの試みは方向性として正しく、今では「遠隔臨場」「リモートサポート」といった形で国や企業が推進しています。
将来的には、工場の保守点検や組立工程、さらには医療や災害現場などでも ARマニュアルが当たり前に使われる未来 が見えてきています。
現状の課題は「デバイス価格」「耐久性」「使いやすさ」ですが、5G環境の普及と技術革新が進めば、現場でも日常的に利用される可能性は高いでしょう。
まとめ マニュアル作成の転機に、3Dデータ活用とAR技術の相性へ期待
マニュアル作成は今、大きな転機を迎えています。
- 第1ステップ:設計工程の3Dデータをマニュアル制作に活用
- 第2ステップ:デジタルマニュアルとして3Dデータを閲覧可能に
- 第3ステップ:AR技術と組み合わせ、現場や遠隔支援での活用へ拡張
ARの最大の強みは、複数人で同じデータを共有しながら、リアルタイムで双方向のコミュニケーションができることです。
これにより、保守点検マニュアル、組立手順書、設置マニュアル、パーツカタログなど、さまざまな領域での活用が期待されます。
今後、デバイスの進化や通信環境の整備が進めば、「場所や時間に縛られない3次元マニュアル」が普及する時代が訪れるでしょう。
ダイテックでは製造業のマニュアル作成改善を検討する際に、考慮すべきポイントをまとめた入門資料「安心と安全をカバーするマニュアルづくり 3つのポイント」「なぜ読むマニュアルから『見る3Dマニュアル』が増えているのか?わかるガイド」をご用意しました。本資料は、マニュアル作成改善をしたい方には必見の資料です。ぜひダウンロードいただき、ご覧ください。